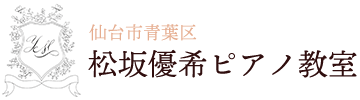音楽エッセイ
音楽エッセイ
前書き
2007年~2008年にかけて、河北新報及び、仙台っこにて連載していた音楽エッセイの一部です。主に留学生活の思い出や、子供時代について綴っています。
オランダでの日々は本当に大変で、でも私にとって宝物のような4年間でした。今読み返してみると、若かりし頃の自分にむず痒さもありますが、あの頃の気持ちをずっと忘れずにいたいと思い、アーカイブに残すことにしました。
音楽の道を志している若い皆さんにとって、私の経験や思いが何かしらのヒントになれば幸いです。
1.昼下がりのショパン

「ピアノを始めたきっかけって何?」
昔から、実に高頻度で聞かれるこの質問。私は大抵「母がピアノをやっていたから」と答え、そうすると皆、あぁなるほど! と大きく頷いてくれる。
母がピアノをやっていたからなんとなくつられて始めたのか、
それとも、母がピアノをやっていたから自分も弾いてみたくなったのか、
はたまた、母がピアノをやっていたから無理矢理習わされたのか……。
考え得る様々な解釈があるけれど、皆がそれぞれどのような想像を介して納得に至っているのか、推量る術はない。物心つくかつかないかの時期だったから、実際のところ、私自身も当時の状況はほとんど覚えていなかったりする。
ただ、そんな中でひとつだけ、鮮明に脳裏に焼きついている記憶がある。
夏の昼下がり、差し込む白い光の中でショパンを奏でる母の姿だ。
一人遊びに飽きた幼い私は、かまって欲しくて最初ごねているのだけど、母の手から魔法のように紡ぎ出される音の世界に、あっという間に引きずりこまれてゆく。
煌めくばかりに美しい旋律。縦横無尽に鍵盤を駆け巡る10本の指。
夢中で聴き入りながら、そのうち衝動的に、目の前の鍵盤を見よう見まねで押してみる。まるで自分も一緒に弾いているようで無性に嬉しかった感覚が、今でも私の中にはっきりと残っている。
あれから年月が経ち、ピアノはいつの間にか、私の生活の一部になった。
反対に、わんぱく小僧がふたり産まれ、母は段々と鍵盤に向かわなくなった。
昔は厳しいことを言われて衝突したりもしたけれど、上京、オランダ留学を経て、彼女も最近では練習にほとんど口を出さない。
「今は優希ちゃんのピアノのファン一号よ」
にこにこしてそう言ってくれる母。でも、彼女こそが私のルーツであり、永遠に超えられぬ存在に他ならないのだ、といつも思う。
楽しいばかりでないこの道だけど、あの夏の日のショパンが、いつでも幸福で温かな記憶と共に、これからも私と私の音楽を支え続けてくれることだろう。
2.因縁の相手

間違いを恐れずに言えば、“相性”というものは人同士に限らず、場所や物など何に対しても必ず存在する、というのが私の持論である。ただ単に嫌いだとか苦手だとか、そういう事ではない。むしろその物事に好感を持っており、こちらから歩み寄ろうと努力しているにもかかわらず、どうにも相容れられない、そんな物の存在を誰しも少なからず持ち合わせているはずだ。海藻(大好きなのにアレルギー)とかブラームス(音型が手にはまらない)とか、私にも幾つかあるのだが、一番の因縁の相手といえば、やはり飛行機に他ならない。
コンクールやコンサートなどで、職業柄、飛行機を利用する機会は多い。オランダに住んでいた頃は年間約20回、多い時で月6回なんていう事もあったのだが、トラブルなく目的地へ到着できたフライトは僅かに数えるほど。確率的にもいかに相性が悪いのかお分かりいただけるだろう。
例えば、初めての国際コンクールでイタリアに行った2003年の冬。見事にロストバゲッジして、ハンドバッグひとつで異国の寒空の下に投げ出されたあの一週間は忘れられない。ドレスや楽譜はすべてトランクの中、加えて視力が0.1もないド近眼なのに、眼鏡までもがなく、カピカピに乾いたコンタクトと僅かな現金のみが命綱であった。しかも、何故か手違いでホテルが予約できておらず、泊まる宿すらないという悲惨さ。途方に暮れて街をさまよい歩いていたところ、偶然にも修道院にたどり着き、「可哀想に。お金はいらないから泊まっていきなさい」と言われ、なんとか凍死せずに済んだのだった。
その他にも悪天候やストライキで定刻通りに飛ばないのは当たり前、酷い時には空港内に爆弾が仕掛けられていると大騒ぎになった事もある。
ここ最近、平和な日本でトラブルのない生活を送っていた私だが、ベルギーでコンサートがあるため、来週渡欧する事になってしまった。因縁の相手との久しぶりの対峙。とりあえず、ドレスと眼鏡は手荷物で持っていこうと思う。
3.私の食日記~オランダ・ベルギー編~

食べる事が好きだ。某週刊誌に連載があるが“私も食日記を書きたい”というのが、かねてからの密かな夢だった。天気、体調、出会った人々や交わした会話――食の記憶は必然的にその日起こった様々な事柄をも付随する。食した物が何であったにせよ、貴重な記録なのだ。
4月12日(土)ロッテルダム
昨晩からオランダ入りし、時差ボケのまま起床。11時、オムレツ入りのベーグルサンドでブランチをとってから母校の音楽院へ。旧友との感動の再会だったはずが、週末ゆえ静まり返った校内。あまりの淋しさにむせび泣きながらひとりで練習する。
夕方、連絡が取れた友人とギリシャ料理店へ。トマトのスープ、鮭とほうれん草のラザニア、キャラメルパフェ。後から他の友人も次々と合流し、結局とても楽しいひと時を過ごす事が出来た。

4月14日(月)ロッテルダム→ブリュッセル
朝、駅前のデリで買った山羊チーズサンドを食した後、凄まじい腹痛と吐き気。しばし悶え苦しむ。午後、教授宅でレッスンのため、鉛のような体を引きずって外出。電車に揺られること2時間、息も絶え絶えで到着するものの、
「How are you?」
と聞かれれば思わず口をついて出てしまうのは悲しいかな
「fine!」
なのが日本人の性で、もう言い訳はできないままレッスン開始。
半ばヤケになって一心不乱に演奏したところ「今までで一番いい演奏だ」とのお言葉。
複雑な心境になるも気がつけばお腹の痛みも消えており、何がなんだか分からないがとりあえず良かった良かったと帰路に着く。大事をとって夕食はパンとクリームスープ。
4月17日(木)アントワープ
いよいよコンサート当日。昨晩から落ち着かない。朝食はクロワッサンとハム、チーズ、本番前のリラックス対策カモミールティー。
11時にリハーサルのため会場へ。古い教会なのだが外観も内部も思った以上に素晴らしい。ステンドグラスから差し込む光の美しさに感動しながら3時間ほど微調整。
15時、チキンのパスタとアップルタルトで遅めの昼食。本番前は炭水化物を多めに摂るのがセオリーだ。
ホテルに戻りお昼寝し、20時半、コンサート開演。緊張で卒倒しそうになるも、なんとか無事に弾き終える事が出来た。
終演後は立食パーティー。別部屋に到着するや否や、先に到着していたお客様に取り囲まれ、感激の涙。と、そうこうしている間にご馳走のお皿は次々と空になり、またも涙。ありつけたのはビスケットとチーズのかけらのみで、心は満たされつつもお腹を鳴らしながら就寝。
4.生涯の師

海外から高名な教授が来日するからと誘われ新宿のスタジオを訪れたのは、18歳になったばかりの冬の日だった。
白い肌に混じり気のない銀髪、グレーのスーツに映える、瞳と同じアクアブルーのネクタイ。“ボンジュール”と微笑み出迎えてくれた彼は、南米の出身だと聞いて思い描いていた私のイメージとは随分違っていて、石鹸なのか香水なのか、辺りには嗅ぎ慣れない外国の香りがほのかに漂っていた。
当時の私は、コンクールでも学校の試験でも満足のゆく結果が得られず、スランプの真っ只中だった。そんな私に、レッスンの後舞い込んだ思いがけないオファー。
「君には光るものがある。自分の元に来て一緒に勉強しないか」
暗闇の中に突如、細くも輝く蜘蛛の糸が舞い降りた瞬間だった。
希望を胸に渡ったヨーロッパの地で、まず私を待ち受けていたのは、頂の見えぬほどにそびえ立つ課題の山だった。
“才能があるんだから、ユキには努力する義務がある”
なかなか手ごたえの感じられぬまま、呪文のように繰り返される教授の台詞はなんだか霞を食うようで、それでも彼の期待に応えたい一心でしゃにむに走った。逃げ場のない異国の地で、彼に見放されたら最後だと必死だった。
ようやく変化が訪れたのは、留学して3年が過ぎた頃からだ。奏でたい理想の音があるのに、それを具現化できない…よく抱いていたそんなもどかしさを、あまり感じなくなっていることにふと気がついた。頭と指先とが確実にリンクする快感。レッスンは俄然楽しくなった。
無我夢中で駆け上ってきた道のりだったけれど、思い返してみれば険しい道中のそこかしこには愛情溢れる道しるべがいつも置かれていて、結局私はすべて見越した彼に導かれるまま、ただその跡を辿ってきただけなのかもしれない。
日本へ帰国して早4年。ゆるやかに流れる日々の中、もう道しるべは見当たらない。
けれどこれからも、しっかり自分の足で歩み続けていきたいと思う。卒業の日、“ユキの事を誇りに思うよ”と言ってくれた彼に対して、いつでもしゃんと胸をはれる自分でいたい、と思っている。
5.ラテン気質

私が四年間留学していたオランダの音楽院には、オランダ人のみならず世界中から沢山の生徒が集まってきていて、肌の色も宗教も様々な彼らが集うキャンパスは、まさに人種のるつぼであった。
学内カフェには、ハローにボンジュール、ニーハオにオラ、と常に多様な挨拶が飛び交い、中国人と日本人が漢字で筆談する隣でイタリア人とポルトガル人が(それぞれお互いの言語で)討論し合う……なんて光景も日常茶飯事。ピアノ科などはむしろオランダ人の方が圧倒的に少数で、学校にいると、ここがオランダであることを忘れてしまう事もしばしばだった。
そんな環境の中、私の周りには何故かイタリア、スペインといったラテン系の友人が多かった。
<ランチの後の選択肢>
コーヒーを飲みに行こう(アメリカ人)
ちょっと一服(ロシア人)
ジェラート食べたい(イタリア人)←ここに便乗。
<コンクールで自分の出番までの空き時間>
他の出演者の演奏を聴こう(日本人)
練習しよう!(韓国人)
一眠りしたい(スペイン人)←ここに便乗。
…といった具合に、どういう訳か彼らとはあらゆる場面において妙に気が合ったのだ。
彼らはいつも陽気でおしゃべりで、自信家かつ楽天家で、そして非常にマイペースだった。反対に、日本人のデフォルトは控えめで真面目なコツコツ型。完全に真逆の性質の我々だけども、だからこそかえってうまくいく…相性とは案外そういうものなのだろう。
しかし、彼らにそう話してみたところ、オーマイゴッドと大袈裟なジェスチャーで天を仰ぎ、それは違うと諭されてしまった。
「自分のことが分かってないなぁ。ユキはこっちサイド!ラテン気質だよ」
確かに、人生まずは楽しくなくちゃ!という彼らのポリシーには実に共感する。が、大和撫子であるはずの私がラテン気質とは…。今でも、まるで腑に落ちないのである。
6.ショパンに寄せて

ヨーロッパに住んでいた五年前の秋、ベネチアを訪れた。
年月によって変色したのであろう赤茶けた石壁の家々をかいくぐり、ゴンドラに揺られる。舟の側壁に体を預け空を見上げれば、そこには一面に広がるコバルトブルーの空。ちゃぷんちゃぷんと一定のリズムで水がたゆたい、まどろみかけた私の視界の中で緑と青が混ざり合って溶けてゆく。
ああ、そうか。突然に、全てを理解した。
―足りなかったのは、この「揺れ」なんだ―。
「どうも違う。硬いんだなぁ」
さかのぼる事、一ヶ月前のオランダ。そこには、ため息をつきながら音楽院を後にする私がいた。ショパンの名曲、舟歌のレッスン。この台詞を言われ続け、一向に先に進めないままもう三週間が経つ。
「これはゴンドラ漕ぎの唄なんだよ。波のたゆみなんだ」
教授は言う。しかし、その感覚がどうしても分からない。苦心すればするほど、波は優雅にたゆたうどころか私をあざ笑うかのようにジャブンジャブンとしぶきをあげ、その船酔いを起こしそうな不愉快さに、未熟な漕ぎ手である私は立ち往生してしまうばかりなのだった。

家にこもって練習してももう埒があかないと、かくして降り立ったベネチアの地。街全体が波打っているかのような揺れに最初こそ戸惑ったものの、半日も経った頃には、その不安定さがかえって心地よく感じられるようになったのだから不思議なものだ。
私の演奏にどうしても足りなかったもの。
それこそ、呼吸をするのと同じようにゆらぎと同調するこの感覚だったのだ。
今年で、ショパンの生誕からちょうど二百年を迎える。奇しくも時は十月十七日、ショパンの命日。ふいに懐かしくなってあの楽譜を引っ張り出してみた。
びっしり書かれた鉛筆書きのひとつひとつを、愛おしくなぞる。真っ黒なページの先には、ショパンの残した永久なる青碧と共に、試行錯誤し続けたヨーロッパでの日々が今でも眩しく広がっている。
7.ステージの魔物

ハロウィンの季節である。十月になると街のあちらこちらにオレンジと黒が溢れ、一昔前まではマイナーな存在だったカボチャお化けも、今やハロウィンの顔として老若男女に認知されるようになった。もしバレンタインが某お菓子会社の策略によって定着したという説が真実であるのならば、ハロウィンの普及の陰にはきっと全国の南瓜農家の暗躍があったに違いない。
冗談はさておき、音楽家のプレイグラウンドにも常に沢山の魔物が潜んでいる。どこからともなく現れステージを引っ掻き回したのち、がっくりとうな垂れる奏者を取り残しあっという間に飛び去ってしまう彼ら。その中から、今日は過去、特に苦戦を強いられてきた3強を紹介したいと思う。
ステージの魔物その1「緊張」…主にパフォーマンスの初期段階に現れる。その攻撃の威力は絶大で、ダメージを受けてしまうと、手足はブルブル、体はガチガチ、お腹はグルグルで目も当てられない状態に。
ステージの魔物その2「疲労」…緊張とは逆に、主にパフォーマンスの終盤に潜む。遅効性の毒薬の如く少しずつ蓄積されてゆくダメージは、許容範囲を超えるとやがて眩暈やふらつきを引き起こす。時に、仲間「雑念」を呼び出す。
ステージの魔物その3「雑念」…一度現れるとなかなか消えない厄介な相手。“♪ドシラ、ドシラ”のパッセージで、脳内でゴジラとメカゴジラの対戦が火蓋を切り、“♪ドレドミレド”では、どうしても某ハンバーガー店のピエロの微笑みが頭をよぎってしまう。
ハロウィンのお化けはお菓子を与えれば退散するけれど、彼らにはそんな子供騙しは通用しない。3種の神器、カモミールティー、栄養ドリンク、ブドウ糖で万全に築いたつもりの防護壁だって、するりとたやすく通り抜けてしまう。彼らに惨敗し、トイレに駆け込んで目を腫らした苦い過去を思うと、今でもステージ袖では及び腰だ。
だけどそんな悪戦苦闘を経て、最近、少しずつ勝率が上がってきた。虎穴に入らずんば何とやら。十分に鍛錬を積んだら、あとはもう、自分を信じ前へ踏み出すしかない。
8.クリスマスの願い

年の瀬も近づくこの季節になると、木枯らしに乗って私の胸をかすめる記憶がある。
零下15度、極寒のオランダで迎えた2004年の冬のことだ。
留学して2年、ふと沸き起こった疑問が私の音楽への情熱を蝕み始めたのはちょうどこの頃だった。走っても走っても前の選手との距離が全く縮まらないマラソンのような、例えるならばそんな感覚。厳しい競争社会の中、必死で努力しても適わない相手がいるのだという現実に直面し、そんな私にこれ以上ピアノを続ける意味が果たしてあるのか、何のためにピアノを弾くのか、その答えが見出せず、徒労感ばかりが募る毎日だった。
交通事故に遭ったのはそんな矢先だった。車に撥ねられ左腕を強打。打撲した腕は小豆色に腫れ上がり、動かすと鈍痛が走った。最初は割と楽観視していて、練習をさぼる口実ができて良かったとすら思った。けれど、しばらく経ってもなかなか腕は治らない。このままピアノが弾けなくなったらどうしようと徐々に焦りが生じ、押し寄せる不安の波に悶えた。心配をかけたくなくて、日本にいる両親には話せなかった。
あの年のクリスマスは今でも忘れられない。ビロードのような静寂に覆われたロッテルダムの街。白夜の影響でぼんやりと明るい藍色の夜空を見上げ、神様に一生の願いごとをした。
プレゼントもケーキも何もいらない、ただもう一度ピアノが弾きたいと、それだけを願った。
ようやく腕が完治したのは、それから2ヵ月後のことだ。再びこの手で音楽を奏でられる幸運に感謝した時、いつの間にか、既にピアノが私の一部になっていたことに気づいた。コンクールで賞をとるためでも、誰かの期待に応えるためでもなく、これからは自分のために、私が私であるためにピアノを弾き続けたいと心の底から思った。
そそっかしくてよく転ぶ私も、あれ以来、手だけは全力で死守するようにしている。バンザイしたまま階段を滑り落ちたりするものだから、気の毒な我が脚は生傷が絶えない。それでも、あんな思いだけはもうこりごりだ。
一喜一憂しながら、これからも音楽と共に生きていきたいと思っている。私の中に、もう迷いはない。
9.小さな世界

先日ディズニーランドを訪れた。一日中駆け回っていた子供の頃とは違い、今は日が暮れてから入園し、パーク内をゆっくりと歩くのが好きだ。あの独特の非日常感の中、色鮮やかに彩られた世界を散策するのは、それだけで充分に楽しい。そんな中、訪れるたび必ず乗りたくなるのがイッツアスモールワールドだ。一歩足を踏み入れれば、つんと鼻に抜ける塩素の匂い。変わらぬ温かさで耳に響くあの歌に、記憶の扉が静かに音を立てる。
“世界中どこだって 笑いあり涙あり みんなそれぞれ助け合う小さな世界”
私が留学していた音楽院のクラスも、各国の生徒が集まる、まさに小さな世界だった。校内のカフェでは幾多の言語が飛び交い、そのざわめきは時に開演前のオーケストラを彷彿とさせた。
一人ぽつんと座っていた私に、最初に声を掛けてくれたトルコ出身のナズリ。物静かなホセと陽気なマリオナは、対照的な性格ながらそれぞれクラスの中心的存在だった。保湿クリーム代わりにと塗ったアロエの汁で全身を腫れあがらせて以来、極度の植物恐怖症になってしまった運のないニコライ。私を見つけるたび駆け寄ってきては、得意満面でドラえもんの歌を熱唱する5つ下のフェルナンドは弟のように可愛く、6ヶ国語を自在に操るクロアチアの才媛マルチナの理知的な演奏には、いつも溜息が漏れた。
年齢も国籍もバラバラなのに、皆驚くほど仲が良かった。週末には誰かしらの家でパーティーが開かれ、手土産に巻き寿司を作っていくと毎回あっという間になくなった。音楽の事、恋愛の事、将来の事。同じように悩みを抱え、泣いたり笑ったりしながら、同じ沢山の時を共有してきた。
卒業後、ニコライは故郷へ戻り、マルチナはドイツに拠点を移した。学校に残りアシスタントとして奮闘しているホセの情報によると、ナズリは石油王にみそめられ、今はアラブで暮らしているらしい。
“世界はせまい 世界は同じ 世界はまるい ただひとつ”
離れ離れになった今、仲間たちが再び集うことは難しい。けれど、どこまでも広がる空を見上げ、それぞれの場所で頑張っている皆を思うと、なんだかふつふつと力が沸いてくる気がするのだ。
10.喜努愛楽

ピアノは初め、私にとって魔法の箱だった。母に弾いてとねだっては、そこから自由自在に音が紡ぎ出されていく様を、僅かな恐れと大きな憧れを持って見つめたものだ。
3歳、やがて自分にも音が出せることを知る。それは一変して大きなおもちゃへと姿を変え、幼い私の遊び相手になった。
小学校時代、教室のオルガンを弾いていると皆が集まってきて、周りが友達でいっぱいになる事が嬉しかった。“ピアノが弾けてすごいね”そう言われ子供らしい自尊心が芽生えて、ピアノはいつしか私の特技になった。中学校に上がってコンクール等に参加するようになると練習もハードにはなったけれども、頑張れば頑張っただけ成果が上がることが面白く、苦とは感じなかった。
壁に突き当たったのは、東京の音楽高校へ入学してからだ。クラスメイト皆がライバルという環境ではピアノはもはや特技でもなんでもなく、熾烈な競争の中、培われていた自信とプライドはがらがらと音を立てて崩れた。世間の女子高生が青春を謳歌している最中、自由を拘束する毎日の練習は次第に疎ましいだけのものとなり、世の中には既にピアノの上手な人が沢山いるというのに、何も見返りもない、ただただ辛いばかりの練習を私が続ける意味が果たしてあるのかと真剣に悩んだ。
そんな時、運命の出会いがあった。
何のためにピアノを弾くのか――まだ答えの見つからないまま、それでも何かが変わることを信じてオランダへと渡った。山積みの課題、高度な要求。毎日が挑戦の連続で、戦うべき相手は他の誰でもない自分自身だった。
逃げ場のない異国の地で、泣いたり笑ったりしながらがむしゃらに音楽と向き合う日々。そのうち、コンクールで勝ちたいとか誰かに認められたいとかではなく、純粋にもっと上手くなりたいと思えるようになった。自分の手で、この素晴らしい音楽を表現したい。感動を伝えたい。
急に光が見えてきたのはそれからだ。
喜努愛楽。私のモットー。
いい時も悪い時も、今まで音楽はずっと私の側にあって、私を支え続けてきてくれた。
ピアノを奏でる喜びを忘れずに、そして音楽への大きな愛を持って、これからも楽しみながら努力を続けていきたいと思う。
ゴールまで、まだまだ先は長い。